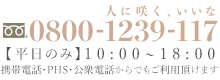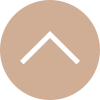2023年5月号
季節を楽しむ
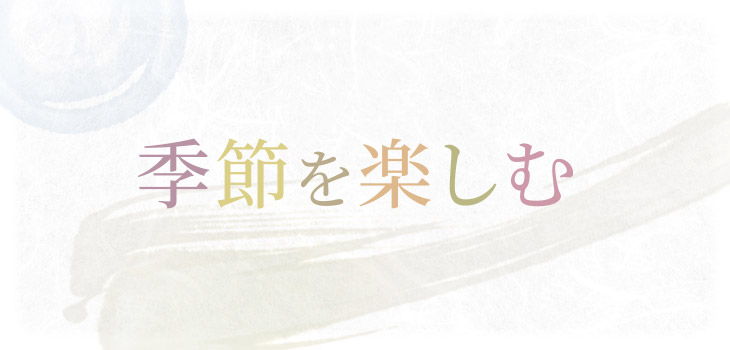
こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
さて、日本の四季を24の節気と72の候にわけ、
それぞれに美しい言葉で表現される
二十四節気と七十二候。
季節ごとに現れる鳥や虫などの生き物や植物、
天候、自然などの、約5日ごとの変化。
それを感じさせてくれるのが七十二候です。
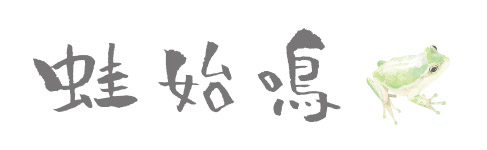
【立夏】 初侯
蛙始めて鳴く(かわずはじめてなく)
5月6日~5月10日頃
日本ののどかな春の風景。
そこには田んぼがあります。そしてその中の蛙が鳴き始める頃。
オタマジャクシからカエルになって、田んぼの中を泳ぎ、活動を始めます。
「かえる」は日常語として、「かわず」は歌語として、
言いわけられてきたそうで、万葉集にも出てきます。
この頃からどんどん鳴き声で賑やかになっていきます。
その声は雄から雌への求愛の声とも言われています。
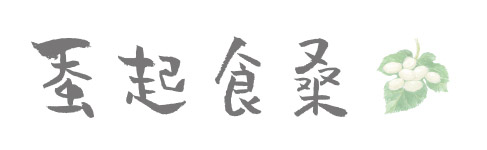
【小満】 初侯
蚕起きて桑を食む(かいこおきてくわをはむ)
5月21日~5月25日頃
美しい絹をつくり出す蚕。実は野生の蛾を人間が飼い慣らし、
数千年かけて家畜化したものらしいのですね。
お蚕さまなどと崇められていますが、
養蚕の歴史は古く、古事記や日本書紀にも書かれているとか。
その蚕が動きはじめ、桑の葉をたくさん食べる頃。
そして蚕の繭からは美しい絹糸がつくられます。

【小満】 次侯
紅花栄う(べにばなさかう)
5月26日~5月31日頃
紅花の花が咲きほこる頃。
染料や口紅、食用油(サフラワー油)などの原料として栽培され、
なんと古代エジプト時代から利用されていたそうです。
日本では奈良時代から栽培されていたらしく、
染料として珍重されてきました。紅花の花言葉は、
『包容力』『特別な人』『愛する力』『化粧』『装い』だそうで、
女性にふさわしい花ですよね。